富東は何故斜面打起しになったか?本当はあまり記したくなかったのですが、この経緯(平成6年6月頃)を具体的に知っており、現在でも弓を引いている者が自分を含め2・3名となってしまいました。県内の一部で誤った情報が流れていた様なので、事実を残すという意味であえて公開しています。 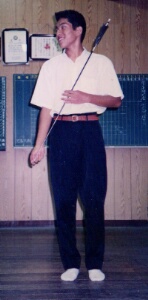 平成6年9月撮影(ちなみに高校2年生) 富東弓道部は、そもそも自分が入部するまでは女子部員のみで構成されていた。道場の壁には昭和52年度卒業生からの名札が掛けられている(旧道場の話。新道場にはありません)。林好一先生の下で正面打起し(二足開き)の射法を行い、県南及び徳島県下の強豪校として名を馳せ、インターハイの団体及び個人競技にも多年にわたり出場していた。1つ上の先輩も県総体団体では準優勝し、県総体で個人準優勝を果たした先輩が、インターハイで準優勝の快挙を達成している。 以上の様な輝かしい伝統を誇る富東弓道部に、入学後直ぐの平成5年の4月に入部した。しかも、初めての男子部員であった。どうして女子生徒しかいない弓道部のドアを叩いたのか?そもそも運動部には入ろうと思っていたが、あまり体が強い方ではなく、静的な運動であると思いこんでいた弓道に目を付けたのである(後にかなりダイナミックな運動であることに気付かされる・・・)。また、母方の祖母が富東の前身である富岡高等女学校の出身で、弓道を受講(この頃は必修科目であり、部活は陸上部であった。)していたり、自分自身シューティングスポーツを強くやってみたいと思っていたことも入部の動機に繋がる。ただ、新入生を集めての部活紹介で、当時の主将が「男子の入部、大歓迎!」と言って呉れなければ、恐らく弓道部には入っていなかったと思う。 入部時の顧問の先生は弓道部に長年携わりながらも、弓道をやったことがない先生であったため、弓の技術は2年生の先輩から教えて頂くこととなる。富東弓道部の基礎を築いた林先生は、自分が入部する1年前の異動で富東を離れていた。数週間後、徒手での射法八節の練習中に、大学院を出たばかりの若い新任の先生が突然弓道場にやってきて、女子の中で男子1人稽古していた自分に声を掛けたのである。何と言ったかは殆ど忘れてしまったが、「男子だけ違う引き方をやってみないか?」(確かこんな感じだったような・・・)と。弓道をやり始めて数週間しか経っておらず、教えて頂けるのなら有り難いと思い、「はい!」と即答。それが斜面打起し、日置流印西派との出会いだった。その若い先生は三年生の先輩から、男子だけ斜面打起しすることへの許可を得ていたとのこと。その後、男子数名が途中入部して団体戦が組めるようになる。自分達は何とも思っていなかったが、外からみれば一種異様であったかもしれない、男子は斜面打起しで女子は正面打起し。後輩が入部するまでは大きな問題もなく時間が過ぎていった。 我々男子部員は形だけの斜面打起しではなく、全ての動作に「どうして?何故?」を求め、全てにおいてその答えが出せるように、書物を読んだり先生に尋ねたりして稽古に臨んでいた。また、和弓の基本特性から、「どのようにすれば狙い所に矢が飛んでいくか?」や、「どうすればもっと早い矢が飛ばせるか?」など、筋骨の働きと和弓の基本特性を絡ませて、言葉が悪いかも知れないが「理論武装」していた。 3年生の先輩が総体を経て引退された。2年生と1年生の新しい部活が始まる。男子は最初から最後まで関与できなかったが、女子の先輩と同期のみで新主将・副将・会計が決定された。男子には不満もあったが、出来て間もない男子部としては、「仕方ない。」という意見が殆どを占めた。部活の当面の目的は新人の育成である。2年生は1年生の育成に精力を傾ける。ただ、今になって思い返せば、林先生が富東から異動されて3年目であり、体系的な正面打起し技術の継承に少々綻びが出ていたように思う。1年生の女子には納得できない気持ちが芽生えていたことも事実だった。女子の上下関係に微妙な隙がこの頃生じ始める。しかし、1年生の男女間の関係は良好であり、また、男子間の上下関係も良好であった。そんなある日、1年生女子の中心的な人物から相談を受けることになる。 「1年生の女子も斜面打起しをやりたいのですが・・・。」 3年になり、新入生が入り、総体があり、引退した。勉強にも打ち込むことなく、毎日部室へ通い、1年生を指導し、弓を引いて帰った。この生活は結局、大学に入学するまで続くこととなる。大学へ入っても、早く帰れる日には部室に顔を出していた。弓のせいだけでは無いが、ついには大学を1年多く行かなければならない事態になってしまった。しかし、何の後悔もしていないし、総体県予選男子団体準優勝、女子個人準優勝、学年別大会優勝、遠的大会個人優勝、結果は出なかったが上手な射手達など、非常に喜ばしい事が多くあった。ただ一時期、現役部員との関係がこじれ、部活内を混乱させ、数年間引きずった問題に関しては、今も反省をしている。 ある日、元顧問の林先生と富東弓道場でお話しする機会に恵まれた。斜面に変わった経緯を詳しく話した所、納得しがたかったのかも知れないが、斜面で引いていくことに理解を示して下さった。ただ、ここ10数年の間に、正面の先生が2名ほど富東へやってきて、富東の技術体系から明らかに外れた技術を生徒に指導し、混乱を招いた事があった。しかしこの背景は、自分との関係をこじらせた現役部員が、審査や試合で出会った正面の先生を富東に招いた事がそもそもの原因であり、富東に来て頂いた正面の先生を非難している訳ではない。また、事実を明らかにすれば、正面の先生の技術を受け入れた多くの生徒は、途中から部活に殆ど来なくなり、総体にだけ出場するも、部室の名札にはその名前は掲げられていない。そもそも練習不足である上に、的中できない理由を富東弓道部に責任転嫁し、稽古を深めて自己の射を改善しようとはせず、部外者である正面の先生の指導で的中を求めるという安易な発想で、正面系の指導を受けるも稽古不足や統一性のない技術体系から的中も出ず、結局自分には何も残らなかったという皮肉な結果が待っていた。 さて、射技指導で一番に考えているのが、富東という学校環境(普通科・商業科が混在するなど)や近年の高校生の生活パターンを考慮した、学校教育の一環としての部活動を重要視するという点である。塾に通う生徒もいれば、バイトに通う生徒もいる。補習の増加や校外模試、検定などなど・・・。部活に割くことが出来る時間は確実に減少している。それはそれで仕方のないことだ。私が卒業後暫くは、試合でバリバリ活躍出来る部活を目指して猛烈に指導した。結果も出たが、時が経つに連れて、自分の指導方法に対して自分自身が違和感を感じ始め、やがて万人が弓を引く楽しみを実感できる指導に変化してきた。部活動は試合や審査で結果を出すために稽古をするのだろうか?自分は違うと思う。試合や審査は目指すモノではなく、目指すべきは自己の弓技を深める事。ひいては自己そのものの精進の筈。試合や審査はあくまでも1つの通過点に過ぎない。また、なかなか接することの出来ない日置流の醍醐味を味わって頂き、卒業後も弓に接して欲しいという願いも込めている。基本的に個人の身体的特徴や進歩状況を考慮して、部員の技術レベルに応じた指導をし、的中の喜びや弓道の奥深さを実感出来るよう努力している。知識面では、弓具の話や、弓道史についても折に触れ話している。 閑話休題。一般の射手に混じって弓を引いていると、富東にまつわる様々な話が耳に入ってくる。親切に教えて下さる人もいれば、自然と人づてに耳に入ってきたりする。大概誇張であったり、一部員の射で富東全体を見たと錯覚している人物の話が殆どである。また、極端な例では、「富東を正面に変える。」と発言した人も居たとか・・・。まあ、武道家としてどーかと思う。自分は思っていることを正直に話してしまう癖があるので、非常に卑怯だと感じてしまう。ひょっとしたら当Siteを見ているかも知れないので、猛省をお願いしたい。そんなに富東弓道部に介入したいであれば、現役部員を説得して変えてしまえば良いのである。ただ、その責任は自分自身で未来永劫背負い、指導をずっと続けて頂きたい。仕事の事情、家庭の事情など関係ない。変えたいと思う気持ちがあれば、そのくらいの覚悟が必要だ。覚悟が無いのであれば安易な発言をするのは慎んで頂きたい。 H19/03/02 (追記:H21/05/16) (追記:H22/06/03)
|